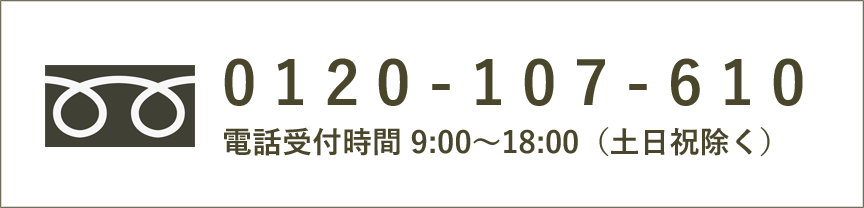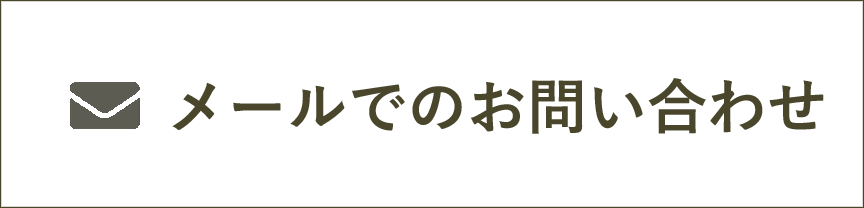テナントの現状回復の
費用相場と対応範囲を
徹底解説
テナントの原状回復工事は退去時に必ず発生します。
居住用物件と異なり、事業用途に応じた設備や造作物の撤去が必要となるため、費用も高額になりがちです。
本記事では、テナントの原状回復における費用相場や対応範囲、居抜き物件特有の注意点など、知っておくべき重要なポイントを解説します。
原状回復工事を円滑に進めるため、ぜひ参考にしてください。
テナントの現状回復の範囲
契約書に基づいた原状回復の範囲
テナントの原状回復は、契約書の内容に基づいて行われます。
居住用物件とは異なり、原状回復の範囲を定めた法的なガイドラインは存在しません。そのため、契約書や特約に記載された内容が、原状回復の範囲を決める重要な基準となります。
契約書では一般的に「賃借人の負担で原状回復を行うこと」と明記され、原状回復の具体的な範囲や方法も記載されています。
経年劣化部分の修繕まで含める「原状回復特約」が設けられているケースもあり、その場合は通常の使用による劣化であっても借主負担となります。
居住用物件とは異なり、原状回復の範囲を定めた法的なガイドラインは存在しません。そのため、契約書や特約に記載された内容が、原状回復の範囲を決める重要な基準となります。
契約書では一般的に「賃借人の負担で原状回復を行うこと」と明記され、原状回復の具体的な範囲や方法も記載されています。
経年劣化部分の修繕まで含める「原状回復特約」が設けられているケースもあり、その場合は通常の使用による劣化であっても借主負担となります。
居住用物件との違い
居住用物件の原状回復は、国土交通省の「原状回復ガイドライン」により
「通常の使用による損耗」は貸主負担
「故意・過失による損傷」は借主負担
と明確に区分されています。
一方、テナント物件の原状回復は、事業用という性質上、原状回復の範囲が広くなる傾向にあります。
内装や設備の変更、専門的な造作物の設置など、事業目的に応じた改修を行うケースが多いためです。
これらの改修部分は、契約終了時に原状回復が必要となるのが一般的です。
「通常の使用による損耗」は貸主負担
「故意・過失による損傷」は借主負担
と明確に区分されています。
一方、テナント物件の原状回復は、事業用という性質上、原状回復の範囲が広くなる傾向にあります。
内装や設備の変更、専門的な造作物の設置など、事業目的に応じた改修を行うケースが多いためです。
これらの改修部分は、契約終了時に原状回復が必要となるのが一般的です。
原状回復が必要な具体例
テナント物件で一般的に原状回復が必要となる箇所は以下の通りです。
・内装の変更(壁紙、床材、天井など)
・店舗用の電気設備や配管の撤去
・エアコンや換気設備などの増設分
・看板やサインの撤去、外壁の補修
・間仕切りの撤去と原状復帰
・専門的な設備(厨房機器、美容設備など)の撤去と床・壁の補修
ただし、貸主との合意により、次の入居者が利用可能な造作物や設備は、原状回復を免除される場合もあります。
原状回復の要否は、必ず貸主と事前に確認することが重要です。
また、原状回復工事は専門的な技術や資格が必要となる場合があり、工事業者の選定にも注意が必要です。
契約書に指定業者の記載がある場合は、その業者に依頼する必要があります。
・内装の変更(壁紙、床材、天井など)
・店舗用の電気設備や配管の撤去
・エアコンや換気設備などの増設分
・看板やサインの撤去、外壁の補修
・間仕切りの撤去と原状復帰
・専門的な設備(厨房機器、美容設備など)の撤去と床・壁の補修
ただし、貸主との合意により、次の入居者が利用可能な造作物や設備は、原状回復を免除される場合もあります。
原状回復の要否は、必ず貸主と事前に確認することが重要です。
また、原状回復工事は専門的な技術や資格が必要となる場合があり、工事業者の選定にも注意が必要です。
契約書に指定業者の記載がある場合は、その業者に依頼する必要があります。
テナントの原状回復にかかる費用
原状回復費用の相場
テナントの原状回復費用は、物件の規模や改装の程度によって大きく異なります。
一般的な相場として、20坪程度の店舗で100万円〜300万円、50坪以上のオフィスでは300万円〜1000万円程度が目安となります。
特に、飲食店や美容室など設備の多い業態は、配管や専門機器の撤去作業が必要なため、費用が高額になる傾向があります。
逆に、事務所など大きな改装を必要としない業態は、比較的費用を抑えることができます。
一般的な相場として、20坪程度の店舗で100万円〜300万円、50坪以上のオフィスでは300万円〜1000万円程度が目安となります。
特に、飲食店や美容室など設備の多い業態は、配管や専門機器の撤去作業が必要なため、費用が高額になる傾向があります。
逆に、事務所など大きな改装を必要としない業態は、比較的費用を抑えることができます。
工事内容による費用の違い
原状回復工事の主な費用内訳は以下の通りです。
・内装解体費:15〜30万円/10坪
・床・壁・天井の修復:20〜40万円/10坪
・電気設備の撤去・修復:10〜30万円/10坪
・給排水設備の撤去・修復:20〜50万円/10坪
・空調設備の撤去:5〜15万円/台
・産業廃棄物処理費:10〜30万円
これらの費用は、物件の状態や地域、工事業者によって変動します。また、急を要する工事の場合は割増料金が発生することもあります。
・内装解体費:15〜30万円/10坪
・床・壁・天井の修復:20〜40万円/10坪
・電気設備の撤去・修復:10〜30万円/10坪
・給排水設備の撤去・修復:20〜50万円/10坪
・空調設備の撤去:5〜15万円/台
・産業廃棄物処理費:10〜30万円
これらの費用は、物件の状態や地域、工事業者によって変動します。また、急を要する工事の場合は割増料金が発生することもあります。
費用を抑えるポイント
原状回復費用を抑えるためには、以下のポイントに注意が必要です。
●契約時に原状回復の範囲を明確にする
入居前に貸主と原状回復の範囲を詳しく確認しておくことで、必要以上の改装を避けることができます。退去時の原状回復工事を最小限に抑えられるため、必ず確認するようにしましょう。
●早めの見積り取得と業者選定
原状回復工事は複数の業者から見積りを取得することが重要です。各社の見積り内容を比較検討することで、適正価格での工事実施が可能になります。また、早めに業者を選定することで、余裕を持った工事計画を立てましょう。
●造作物・設備の譲渡交渉
店舗で使用している造作物や設備のうち、次の入居者が使用可能なものは、貸主や次の入居者への譲渡を検討しましょう。譲渡が成立すれば、撤去費用を大幅に削減できます。
●工事の時期を柔軟に調整
工事業者は繁忙期を避けることで、比較的安価な費用での工事が可能です。
可能な限り工事時期を調整することで、コストダウンを図れます。
可能な限り工事時期を調整することで、コストダウンを図れます。
居抜き物件の原状回復は何が違う?
居抜き物件とは
居抜き物件は、前のテナントが使用していた設備や造作物がそのまま残された物件です。
飲食店の厨房設備や美容室のセット面、オフィスの間仕切りなど、業態に応じた設備が設置された状態で借りることができます。通常の物件と比べて初期費用を抑えられる点が特徴です。
飲食店の厨房設備や美容室のセット面、オフィスの間仕切りなど、業態に応じた設備が設置された状態で借りることができます。通常の物件と比べて初期費用を抑えられる点が特徴です。
居抜き物件の原状回復の特徴
居抜き物件の原状回復は、前テナントの設備や造作物をどう扱うかがポイントとなります。通常、これらの設備は「現状有姿」での契約となり、退去時は借りた時の状態を基準に原状回復を行います。
スケルトン状態まで戻す必要はなく、入居時の状態まで戻せばよいため、原状回復費用を抑えられる可能性があります。ただし、物件の状態や契約内容によっては、前テナントの造作物の撤去が必要になるケースもあります。
スケルトン状態まで戻す必要はなく、入居時の状態まで戻せばよいため、原状回復費用を抑えられる可能性があります。ただし、物件の状態や契約内容によっては、前テナントの造作物の撤去が必要になるケースもあります。
原状回復における注意点
居抜き物件の原状回復で特に注意が必要なのは、入居時の物件状態の記録です。設備や造作物の状態、傷や汚れの有無を詳細に記録し、写真撮影をしておくことをお勧めします。
また、以下の点についても事前確認が重要です。
・設備や造作物の所有権の所在
・修繕や メンテナンスの責任範囲
・故障や破損時の対応方法
・退去時に撤去が必要な設備の有無
これらの確認を怠ると、退去時に予期せぬ費用が発生する可能性があります。
契約前に貸主としっかりと協議し、書面で合意を取ることが望ましいでしょう。
また、以下の点についても事前確認が重要です。
・設備や造作物の所有権の所在
・修繕や メンテナンスの責任範囲
・故障や破損時の対応方法
・退去時に撤去が必要な設備の有無
これらの確認を怠ると、退去時に予期せぬ費用が発生する可能性があります。
契約前に貸主としっかりと協議し、書面で合意を取ることが望ましいでしょう。
テナントの現状回復における注意点
事前確認が必要な項目
テナントの原状回復を円滑に進めるには、以下の項目を必ず確認しておく必要があります。まず契約書を確認し、原状回復の範囲や条件を把握しましょう。
特に重要なのは、指定工事業者の有無です。多くの物件で工事業者が指定されており、その場合は必ずその業者に依頼する必要があります。また、原状回復工事の内容や見積りについても、貸主の承認が必要になることがあります。
特に重要なのは、指定工事業者の有無です。多くの物件で工事業者が指定されており、その場合は必ずその業者に依頼する必要があります。また、原状回復工事の内容や見積りについても、貸主の承認が必要になることがあります。
退去時のスケジュール管理
原状回復工事は想定以上に時間がかかることが多いため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。一般的な流れは以下の通りです。
・退去の3ヶ月前:貸主への退去通知、工事業者の選定
・2ヶ月前:現地調査、見積り取得
・1ヶ月前:工事内容の確定、貸主との協議
・退去後:原状回復工事の実施、貸主の確認、引き渡し
・退去の3ヶ月前:貸主への退去通知、工事業者の選定
・2ヶ月前:現地調査、見積り取得
・1ヶ月前:工事内容の確定、貸主との協議
・退去後:原状回復工事の実施、貸主の確認、引き渡し
トラブルを防ぐために
原状回復工事に関するトラブルの多くは、事前の確認不足や記録の不備が原因です。
まずは入居時に、床や壁の傷、建具や設備の状態を写真や動画で記録しましょう。
この記録があれば、「元からあった傷」と「入居後についた傷」の区別が明確になり、無用なトラブルを防ぐことができます。
また、原状回復工事の内容や見積りは必ず書面で残しましょう。
口頭での約束は後々のトラブルの原因となるため、貸主との協議内容は議事録を作成し、双方で確認することをお勧めします。
工事完了時には貸主立会いのもと確認を行い、原状回復が適切に完了したことの確認書を作成することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
工事期間中の立ち入り制限や騒音対策など、近隣への配慮も重要です。
特に、テナントビルの場合は他の店舗への影響も考慮し、工事時間や搬出入の時間帯について、ビル管理者と事前に調整することをお勧めします。
まずは入居時に、床や壁の傷、建具や設備の状態を写真や動画で記録しましょう。
この記録があれば、「元からあった傷」と「入居後についた傷」の区別が明確になり、無用なトラブルを防ぐことができます。
また、原状回復工事の内容や見積りは必ず書面で残しましょう。
口頭での約束は後々のトラブルの原因となるため、貸主との協議内容は議事録を作成し、双方で確認することをお勧めします。
工事完了時には貸主立会いのもと確認を行い、原状回復が適切に完了したことの確認書を作成することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
工事期間中の立ち入り制限や騒音対策など、近隣への配慮も重要です。
特に、テナントビルの場合は他の店舗への影響も考慮し、工事時間や搬出入の時間帯について、ビル管理者と事前に調整することをお勧めします。
京都のテナントを多数ご紹介
テナントの原状回復は、契約書に基づいて範囲が決定され、居住用物件とは異なり事業用途に応じた広範な対応が必要です。
費用は物件規模や業態によって大きく異なりますが、20坪の店舗で100万円〜300万円程度が目安となり、早めの準備と適切な記録管理が重要です。特に居抜き物件の場合は、設備や造作物の扱いを事前に確認し、入居時の状態をしっかりと記録しておくことで、スムーズな原状回復が可能となります。
京都のテナントを豊富に取り扱っている【テナントプラザ】では、テナントの仲介だけではなく開業サポートからトータルサポートを承ります。
飲食店や美容系サロン、物販店、アミューズメント施設、オフィスなど様々なタイプのテナントがあり、ご要望に沿った提案を心がけております。
ホームページでは取り扱い物件を豊富に掲載しておりますので、気になる物件が見つかった際はお気軽にお問合わせ下さい。
掲載物件に限らず、条件やご希望を伺った上でより良い物件の提案ができれば幸いです。
費用は物件規模や業態によって大きく異なりますが、20坪の店舗で100万円〜300万円程度が目安となり、早めの準備と適切な記録管理が重要です。特に居抜き物件の場合は、設備や造作物の扱いを事前に確認し、入居時の状態をしっかりと記録しておくことで、スムーズな原状回復が可能となります。
京都のテナントを豊富に取り扱っている【テナントプラザ】では、テナントの仲介だけではなく開業サポートからトータルサポートを承ります。
飲食店や美容系サロン、物販店、アミューズメント施設、オフィスなど様々なタイプのテナントがあり、ご要望に沿った提案を心がけております。
ホームページでは取り扱い物件を豊富に掲載しておりますので、気になる物件が見つかった際はお気軽にお問合わせ下さい。
掲載物件に限らず、条件やご希望を伺った上でより良い物件の提案ができれば幸いです。
テナントの審査はどのような点が確認される?
審査の流れや必要書類、ポイントを解説